情報スキルは、これからの時代を生きる力になる
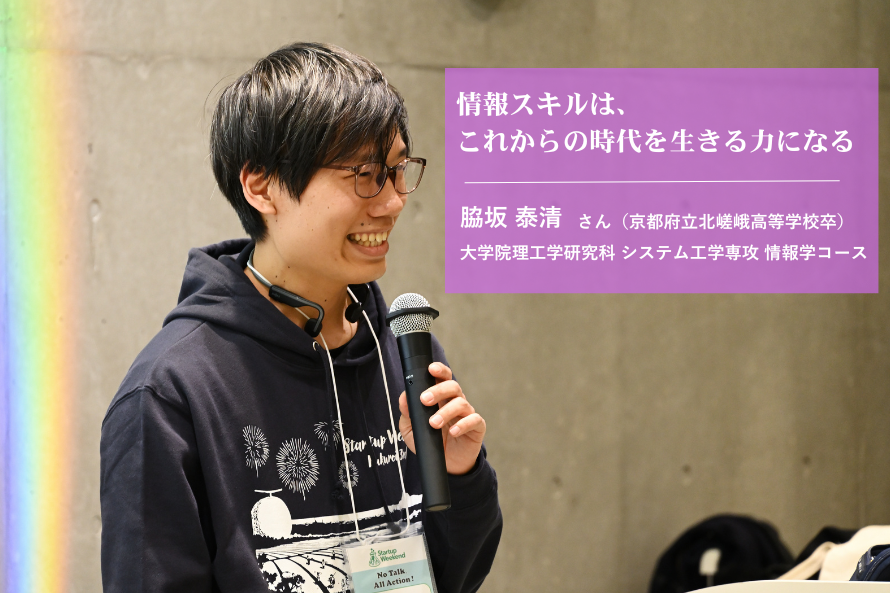
理工学研究科システム工学専攻 情報学コース 1年
脇坂 泰清 さん (本学情報学部、京都府立北嵯峨高等学校卒)
脇坂 泰清 さん (本学情報学部、京都府立北嵯峨高等学校卒)
■大学の研究がきっかけで生まれたビジネス
静岡理工科大学大学院に在籍する脇坂さんは、在学中に「株式会社Azran」を共同創業しました。起業のきっかけは、研究室での活動でした。
「僕が所属するデータサイエンス・人工知能研究室では、2Dの写真から高精度な3D空間を構築する技術の研究を行っています。この研究を進める中で、企業との連携が生まれ、動画を活用したマニュアル作成のニーズがあることを知りました。
中小企業の現場では、新人研修や業務の引き継ぎが課題になっていました。特に、ベテラン社員の技術やノウハウがうまく伝わらないことが多いということがわかりました。そこで、動画マニュアルを活用すれば、効率的に情報を共有できるのではと考えました。」
静岡理工科大学大学院に在籍する脇坂さんは、在学中に「株式会社Azran」を共同創業しました。起業のきっかけは、研究室での活動でした。
「僕が所属するデータサイエンス・人工知能研究室では、2Dの写真から高精度な3D空間を構築する技術の研究を行っています。この研究を進める中で、企業との連携が生まれ、動画を活用したマニュアル作成のニーズがあることを知りました。
中小企業の現場では、新人研修や業務の引き継ぎが課題になっていました。特に、ベテラン社員の技術やノウハウがうまく伝わらないことが多いということがわかりました。そこで、動画マニュアルを活用すれば、効率的に情報を共有できるのではと考えました。」

■大学生でも会社を作れる? その一歩とは
「事業のアイデアは生まれたものの、学生が会社を作るのは簡単なことではありませんでした。そこでまずは、起業に関する情報を集めようと、仲間と学生向けのビジネスコンテスト『足軽ピッチ』に参加し、優勝賞金を得たことが大きな転機となりました。また、大学の『学生活動プロジェクト』から資金援助を受けることもできました。
こうしたサポートを活用し、2024年8月に会社を設立。現在は3人の共同創業者で運営しています。社長を務めるのは起業志向の強いメンバーで、僕を含む他の2人はそこに就職しながら関わっています。
周りの大人に相談することで、想像以上に支援があることを知りました。大学生だからといって尻込みせず、自分のやりたいことがあれば、まずは動いてみることが大切だと思います。」
「事業のアイデアは生まれたものの、学生が会社を作るのは簡単なことではありませんでした。そこでまずは、起業に関する情報を集めようと、仲間と学生向けのビジネスコンテスト『足軽ピッチ』に参加し、優勝賞金を得たことが大きな転機となりました。また、大学の『学生活動プロジェクト』から資金援助を受けることもできました。
こうしたサポートを活用し、2024年8月に会社を設立。現在は3人の共同創業者で運営しています。社長を務めるのは起業志向の強いメンバーで、僕を含む他の2人はそこに就職しながら関わっています。
周りの大人に相談することで、想像以上に支援があることを知りました。大学生だからといって尻込みせず、自分のやりたいことがあれば、まずは動いてみることが大切だと思います。」
■事業の柱は“動画マニュアル”と“プログラミング教育”
Azranの主力サービスは、中小企業向けの動画マニュアル作成プラットフォームです。動画を活用することで、従業員の業務習得をスムーズにし、会社の生産性向上に貢献します。
「僕たちは、ただ動画を撮るだけでなく、誰でも簡単にマニュアルを作成・管理できる仕組みを提供しています。これにより、現場で働く人々が使いやすく、継続的に活用できるツールになります。また、プログラミング教育の受託運営も事業の大きな柱の一つです。静岡県内や仙台で、小中学生向けのプログラミング講座を実施しています。実は、今の収益の大部分はプログラミング教育事業から生まれています。短期間で収益を出すのは難しいですが、少しずつ形になっていると実感しています。」
Azranの主力サービスは、中小企業向けの動画マニュアル作成プラットフォームです。動画を活用することで、従業員の業務習得をスムーズにし、会社の生産性向上に貢献します。
「僕たちは、ただ動画を撮るだけでなく、誰でも簡単にマニュアルを作成・管理できる仕組みを提供しています。これにより、現場で働く人々が使いやすく、継続的に活用できるツールになります。また、プログラミング教育の受託運営も事業の大きな柱の一つです。静岡県内や仙台で、小中学生向けのプログラミング講座を実施しています。実は、今の収益の大部分はプログラミング教育事業から生まれています。短期間で収益を出すのは難しいですが、少しずつ形になっていると実感しています。」

■起業することで見えた“仕事のリアル”
学生のうちに起業したことで、脇坂さんは「働くこと」のリアルを知ることができました。
「ビジネスは、アイデアだけでは成り立たないことを実感しました。実際にお金を稼ぐには、顧客のニーズを正しく理解し、価値を提供し続けることが重要です。また、いきなり大きなことをしようとせず、最初は、無料でできることから始めるのがいいと思います。例えば、SNSで情報を発信する、身近な人にサービスを試してもらう、イベントに参加してみるなど。小さく始めて、少しずつ大きくしていくことが成功のカギです。学生のうちに起業して、もし失敗しても学生に戻るだけですから実はリスクは少ないんです。その意味でもまずは行動してみることが大切だと思います。」
学生のうちに起業したことで、脇坂さんは「働くこと」のリアルを知ることができました。
「ビジネスは、アイデアだけでは成り立たないことを実感しました。実際にお金を稼ぐには、顧客のニーズを正しく理解し、価値を提供し続けることが重要です。また、いきなり大きなことをしようとせず、最初は、無料でできることから始めるのがいいと思います。例えば、SNSで情報を発信する、身近な人にサービスを試してもらう、イベントに参加してみるなど。小さく始めて、少しずつ大きくしていくことが成功のカギです。学生のうちに起業して、もし失敗しても学生に戻るだけですから実はリスクは少ないんです。その意味でもまずは行動してみることが大切だと思います。」
■社会の課題を見つけ、解決する力を
脇坂さんが起業できた一つの理由、それは“情報スキル”修得で培った力がベースになっているという。
「大学でプログラミングやデータから世の中に役立つ答えを見つける情報技術を学ぶことで、単なる知識にとどまらず、『自分で仕組みをつくる力』が身につきます。
プログラミングやデータ活用などのスキルは、ただツールを使えるようになるだけでなく、『社会にある課題にどう向き合い、どう形にするか』を考える力にもつながっています。情報分野の学びは、これからの時代に必要不可欠な“問題解決力”を養う土台です。社会が大きく変化していく中で、自ら考え、行動できる力は、きっとどんな場面でも強みになると感じています。」
脇坂さんが起業できた一つの理由、それは“情報スキル”修得で培った力がベースになっているという。
「大学でプログラミングやデータから世の中に役立つ答えを見つける情報技術を学ぶことで、単なる知識にとどまらず、『自分で仕組みをつくる力』が身につきます。
プログラミングやデータ活用などのスキルは、ただツールを使えるようになるだけでなく、『社会にある課題にどう向き合い、どう形にするか』を考える力にもつながっています。情報分野の学びは、これからの時代に必要不可欠な“問題解決力”を養う土台です。社会が大きく変化していく中で、自ら考え、行動できる力は、きっとどんな場面でも強みになると感じています。」
起業イベントを主催

2025年2月15日(金)~17日(日)、本学および袋井市内の会場で「第3回スタートアップウィークエンド」が開催され、本学の学生が運営および参加しました。
本イベントのリードオーガナイザー(運営代表者)を務めたのは、本学大学院1年の脇坂泰清さん。オーガナイザーとして、大学院2年の柴田浩平さんも運営に携わりました。
「スタートアップウィークエンド」は、新規事業の立ち上げを体験できる起業イベントです。起業を志す人、新規事業に興味がある人、仲間を見つけたい人など、スタートアップに関心のある一般の方々が参加しました。本学からも学生5名が参加し、実践的な学びを得ました。
脇坂さんは「ゼロからイチを生み出すイベントなので、自分が何をしたいのか、それが社会にどのように貢献できるのかを考える経験をしてほしい。また、今回で築いたコミュニティを今後も活かしてほしい」と語ります。
参加者は約30名。地域の自治体や企業家のほか、他県の大学生も参加し、幅広い交流が行われました。
なお、審査委員として木村雅和学長も参加しています。
本イベントは今後も定期的な開催を予定しており、さらなる本学学生の参加が期待されます。
※スタートアップウィークエンドとは?
スタートアップウィークエンド(以下、SW)とは、週末の三日間を活用してアイデアをカタチにする「スタートアップ体験イベント」です。
SWは初日の夜にみんながアイデアを発表するピッチから始まります。そしてハスラー・ハッカー・デザイナーの役割に分かれてチームを組み、最終日の夕方までにユーザーエクスペリエンスに沿った、必要最小限のビジネスモデルを一気に作り上げます。ハスラーは顧客開発を、ハッカーは機能開発を、デザイナーは使いやすいデザインを担当します。(スタートアップウィークエンド袋井 公式ページより引用)
本イベントのリードオーガナイザー(運営代表者)を務めたのは、本学大学院1年の脇坂泰清さん。オーガナイザーとして、大学院2年の柴田浩平さんも運営に携わりました。
「スタートアップウィークエンド」は、新規事業の立ち上げを体験できる起業イベントです。起業を志す人、新規事業に興味がある人、仲間を見つけたい人など、スタートアップに関心のある一般の方々が参加しました。本学からも学生5名が参加し、実践的な学びを得ました。
脇坂さんは「ゼロからイチを生み出すイベントなので、自分が何をしたいのか、それが社会にどのように貢献できるのかを考える経験をしてほしい。また、今回で築いたコミュニティを今後も活かしてほしい」と語ります。
参加者は約30名。地域の自治体や企業家のほか、他県の大学生も参加し、幅広い交流が行われました。
なお、審査委員として木村雅和学長も参加しています。
本イベントは今後も定期的な開催を予定しており、さらなる本学学生の参加が期待されます。
※スタートアップウィークエンドとは?
スタートアップウィークエンド(以下、SW)とは、週末の三日間を活用してアイデアをカタチにする「スタートアップ体験イベント」です。
SWは初日の夜にみんながアイデアを発表するピッチから始まります。そしてハスラー・ハッカー・デザイナーの役割に分かれてチームを組み、最終日の夕方までにユーザーエクスペリエンスに沿った、必要最小限のビジネスモデルを一気に作り上げます。ハスラーは顧客開発を、ハッカーは機能開発を、デザイナーは使いやすいデザインを担当します。(スタートアップウィークエンド袋井 公式ページより引用)
